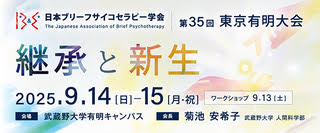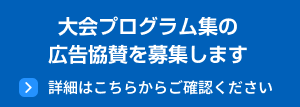大会企画シンポジウム1
9月5日(金) 15:30~18:00
「精神分析と家族療法」
シンポジスト
中村伸一(中村心理療法研究室)
渡辺俊之(渡辺医院/高崎西口精神療法研修室)
上別府圭子(国際医療福祉大学大学院)
司会
中野真也(国際医療福祉大学/心理技術研究会)
指定討論
児島達美(KPCL)
本シンポジウムは、挙げられたテーマの中から精神分析的なエッセンスをくくりとしたものです。交流のある中村伸一氏、渡辺俊之氏、上別府圭子氏の3人をシンポジストとし、以下のテーマで話題提供を行い、議論を行います。
中村伸一:「夫婦家族療法は極めて有効な常識的介入(下坂幸三)である」
下坂幸三は本学会の設立メンバーの一人である。彼は長年個人開業医としてとりわけ重篤な摂食障害の治療にあたってきた。本学会設立以降は患者を含む家族との面接(「家族療法ではなく家族面接」)を重視し、多いに手ごたえを感じ、その経験をいくつかの著作に表している。本発表では、彼の臨床的思索の一つの結論として、悩める家族への「常識的介入」であると言わしめた家族面接のあり方を紹介したい。
渡辺俊之:「私の中にいる二人の家族療法家ーRD.レインと狩野力八郎ー」
対人援助職を選択する背景には、個人的要因、外的要因(教育・研修)、そしてこの2つが出会うするタイミング(年齢や環境)が影響する。
私は大学に入学するまで精神科医に全く関心がなかった。大学入学後に母がうつ病で入院して、多少は関心が向いた。母の主治医は私を病院に呼び、私を「診察」したのである。私は自分に流れる精神障害の血を確認されたような思いになった。その帰り本屋で「狂気と家族」と「引き裂かれた自己」を買い、RD.レインは私の心に住み着いた。一時的に反精神医学熱が冷めた時もあったが、自分を知ろうと精神科医を志したのである。卒業して入った母校の研修先が、狩野力八郎氏率いる力動的入院治療病棟だった、境界例ばかりの病棟で、私は手厚い研修を受け内省への道が開け力動的精神科医へ進むことになる。二人が精神分析と家族療法で繋がっていたことを知るのは随分たってからだった。彼らの存在は今でも私に影響を与えている。
上別府圭子:「土居健郎先生から教わった家族との関わり方」
私は漠然とではあるが、「人」や「人の生活」にアプローチする領域に進もうと思って、大学3年生で「医学部保健学科」を選び進学した。そこには7つの分野(研究室)があって、栄養学や母子保健学、人類生態学等は名前の印象とは違ってどちらかというとラボ系で、中でもいちばん臨床っぽいことをしていそうな「精神衛生学分野」に関心をもった。記憶違いかも知れないが、当時は教員の豊富な教室で、精神分析系の先生だけでも3名(土居先生、吉松和哉先生、大橋秀夫先生)、いらっしゃった。ただ土居先生は「僕は東大では精神分析はやらないよ」とおっしゃっていた(と、後輩に聞いた)。私が見たり聞いたりしたものは何だったのか、思い出しながら、原点に立ち戻ると共に、現代の臨床にどう活きるのかについて考えてみたい。
大会企画シンポジウム2
9月6日(土)10:10~12:10
「さまざまな領域における家族療法の活用」
シンポジスト
福山和女(ルーテル学院大学)
生島浩(福島大学)
後藤雅博(こころのクリニック ウィズ)
司会
市橋香代(東京大学医学部附属病院)
家族療法は“さまざまな要素が相互作用する全体”とされるシステム論的な認識論をもとに発展してきました。それゆえ、家族療法的な視点は、家族との合同面接における直接的な治療・支援に留まらず、本人・家族に関わる関係者、集団・組織などへも適用され、さまざまな領域で活用されています。本シンポジウムは、さまざまな領域における家族療法の活用として、ソーシャルワーク、非行臨床、家族心理教育についてとりあげ、各領域における取組やその有用性を検討し、家族療法やその視点の活用と可能性について議論を行います。
福山和女:ソーシャルワークと家族療法 – システム論の適用
1970年代、日本にマレー・ボーエンの家族システムズ論が紹介された。その理論は、1954年代から3年かけて研究されたものである。当時、システムとして家族を理解することの視点を実践に適用するのはとても難しいものであった。また、支援介入を家族にと試みたが、ソーシャルワーク相談には、青少年の家庭内暴力、家出・非行が増えてきた。家族への支援と謳っているはずのスタッフは、問題行動を呈している子ども本人に焦点を当て、子どもが家族に依存していることを問題であると捉えた。「家族のしがらみからの自立」として、自立支援が開始された。家族全員にアプローチする必要性を唱え、全員の面接参加を求めたが、特に父親が拒否した。スタッフチームは父親へのアプローチの仕方について議論したが結果は絶望的であった。
ソーシャルワークの領域への家族療法導入の意義について皆さんと共に考えたい。
生島浩:非行・犯罪臨床における家族支援-システムズ・アプローチの展開
少年非行・成人犯罪の立ち直り支援として「家族療法」を活用したシステムズ・アプローチ(体系的かつ組織的な取り組み)について,私の40年に及ぶ臨床実践,特に近年注力している矯正施設出所者の引受人(家族)会の機能分析について述べたい。多機関連携での運営が特質だが,本人とともに支援対象者である家族もまた医療や福祉機関の関わりが必須であり,地域生活支援の観点を重視している。
さらに,警察・児童相談所・家庭裁判所・保護観察所・少年院などの専門機関における家族支援の現状と課題を概説したい。小児期逆境体験(ACE)やトラウマインフォームド・ケアなど本人の被害者性への配意は,家族の加害者性への着目につながるリスクを内包しており,司法・犯罪領域における「家族を要因とせず,手立てとする立ち直り支援」の行く末を案じている。
後藤雅博:家族心理教育(これからの家族とのco-design、co-productionの方向性について)
家族心理教育は疾患、障害などの知識・情報を家族と共有し問題解決に当たる家族支援法である。その歴史はアメリカの脱施設化に伴う1970年代に遡るが、当時は重症の精神障害者の地域生活を維持し再発・再入院を防ぐことに主眼が置かれエビデンスも集積された。その構造は①精神障害やエイズなど受容しにくい問題を持つ人たちに(対象)②正しい知識や情報を心理面への十分な配慮をしながら伝え(方法1)③病気や障害の結果もたらされる諸問題・諸困難に対する対処方法を習得してもらうことによって(方法2)④主体的に療養生活を営めるよう援助する方法(目標)とされてきた。しかし近年の精神医療や障害者を取り巻く状況の変化により、対話と双方向性が重視され、家族は「苦労」の専門家であり家族心理教育は専門家同士の語り合いであるとする協働創造(co-production)的アプローチを目指すようになってきている。そういう方向こそが支援の基本であることを確認したい。