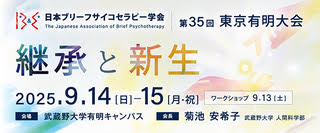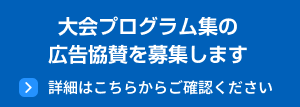大会長講演
9月5日(金)10:00~10:50
大会長講演 「家族療法-温故知新-」
講師:中野真也(国際医療福祉大学/心理技術研究会)
司会:岩田尚大(広島大学病院)
大会プログラムのスタートとして、昔の家族療法の実践を振り返ってみます。マスターセラピストの実践は、一見するとおとぎ話や名人芸のように思われるかもしれません。ですが、実際の事例では、困難な問題・疾患に立ち向かい、改善・解決するストーリーには、それが成立するだけのポイントが含まれているはずです。どんな視点や技術が必要か。他のアプローチとの違いは何か。具体例を取り上げ、家族療法の基礎なるものを取りだす試みをしてみます。そしてマスターセラピストの実践を雲の上の存在にするのではなく、それに近づくための道筋を考えて提起してみたいと思います。さらに欲を言えば、一般には馴染みにくく、やや誤解も生じやすい家族療法のポイントをリフレイムして活用しやすいように、とチャレンジしてみます。
古くからあるものを温めて、新しきを知る。家族療法の基礎的かつ重要なポイントは、決して色褪せることなく、現在・未来へとつながり、家族や関係者、支援者たちが協力し、困難な問題に取り組んでいくのを助けるものになる。その一歩になれば、と期待して。
学会長講演
9月5日(金)11:00~12:00
学会長講演 「日本家族療法学会に期待すること」
講師:村上雅彦(広島ファミリールーム)
司会:中野真也(国際医療福祉大学/心理技術研究会)
1、はじめに
この度第13代会長に就任いたしました。家族療法学会の発展に少しでも貢献できるよう精一杯務めて参りたいと考えております。私の思いとしては、理事の方々、そして会員のみなさまと一丸となって、取り組んでいきたいと思っております。なにとぞよろしくお願い申し上げます。
2.家族療法との出会い
今大会のテーマが温故知新ということもありますし、私のご紹介代わりに、まず、私の家族療法との出会いについてお話しさせていただきます。
3.日本家族療法学会への期待
会長としての抱負を述べたいと思います。
柱は3つで、1.家族族療法の普及、2会員のレベルアップ、3社会貢献、です。
1)家族療法の普及
家族療法は治療法としても家族支援の方法としてもとても効果的な方法を持っています。しかし、残念ながらその効果の高さについて知って下さっている方はまだまだ少ないと思います。
2)会員のレベルアップ
家族療法がとてもいい方法だとしても、臨床においても、研究においても、そのことをしっかり実践している人が増えていかなければそれを示すことができません。
私がここまで責任者として取り組ませていただいたこととして、家族療法資格認定制度(認定スーパーヴァイザー、認定ファミリー・セラピスト)があります。ぜひこの機会に詳しく知っていただきたいと思います。
3)社会貢献
私は、家族療法が困っている方に役立つことが一番大事なことと思っています。しかし、残念ながら、家族療法がどんな有効性があるのか、何に役立つのか、一般の方々にそこまで知られている状況にはなっていないのではないかと思います。
4.おわりに
みなさまそれぞれに家族療法との出会いのストーリーがあり、何かを求めて学会に入会されたことと思います。その思いを実現していくために、学会がどう発展していけばいいのか、できれば会員1人1人のお考えを反映できるような、よりよい学会に発展させていくことができればと考えております。ぜひともご協力いただきますようお願い申し上げます。
大会企画講演1
9月6日(土)14:00~15:00
マイケル・ホワイトの詩学 隠喩と換喩
講師:小森康永(愛知県がんセンター精神腫瘍科部)
司会:坂本真佐哉(神戸松陰大学)
マイケルが面接中に頭の中で何が起こっているのかを問われ、自分の聴き方は、仕事に対する自分の好みのメタファーによってもたらされる、特に詩学がしっくりくると答えたことからこの話は始まります。
大会企画講演2
9月6日(土)15:45~17:15
「患者カルテ」の理論と実践――ナラティヴ、コラボレイティヴ、オープンダイアローグの展開
講師:野村直樹(名古屋市立大学大学院人間文化研究科)
司会:浅野久木(医療法人成精会刈谷病院)
「患者カルテ」は、その名のとおり患者が書くカルテを指します。正式名は、Patient-Authored Medical Record(患者が著す医療記録)で、「患者カルテ」はその通称です。ただ、精神科患者がひとり机に向かって書くというのではないです。看護師が対話する場を確保し、患者は「自分はどうしたら治るか」というテーマを中心に自分自身を語るのです。看護師はそれを聞き、質問を投げかけ、手元のパソコンにその語りを打ち込んでいきます。そこに一つ文体があります。主語を「ぼくは、私は」という「患者本人の一人称」にして看護師は書きます。対話を終えるにあたり、書かれたことを患者が確認し、訂正し、あるいは加筆して、その文書を承認します。これが「患者カルテ」です。それをコピーして患者に渡します。この共同文書の著者は患者と看護師で、両者が同意すればその「患者カルテ」は外部と共有されます。
この「患者カルテ」を精神科の新たな治療ツールとして開発するのが私たちの取り組みです。なぜ患者は自分の処方箋を書く必要があるのか、精神科医という専門家たちがいるにもかかわらず。答えは、アーサー・クラインマンが「疾患」(disease)に対して「病い」(illness)を切り分けたことに由来します。「疾患」は診断学に基づいた医師の見解であり、「病い」は患者が経験する苦痛や不都合のストーリー(物語)です。この二つは明らかに違ったものですが、苦悩の物語を誰かが聞き、その物語が書き換わっていくことに立ち会うことで、患者は症状があったとしても楽になっていくと思われます。
「病い」の語りを聴くのは大事だけれど、どうやって聴くのですか?どうしたら患者は自分の治し方を語ってくれますか?そもそも患者にそれがわかるのですか?ここでは看護師は相手のことを決めつけることなく、悩みを内包するその人生については知らないので、聞き手として生徒のように「教えてもらう」という「無知の姿勢」で臨みます。すると、そこから会話は推進力を得て広がります。「無知の姿勢」は、ハリー・グーリシャンによって発案された治療的会話のスタンスですが、なぜこれが治療的に作用するかというと、「無知の姿勢」から発せられた質問が患者の語りをそれまでにない物語へと改訂する機会を与えるからです。そのように書き換えられていく物語と回復のプロセスが相関します。好奇心をもって更に聞くと、その応答として患者のストーリーはさらに整合性を増し豊かになります。そのように物語と対話の発展が「治療的」と定義されます。
その後、患者と看護師は参加者を選び(例、医師、家族、他の医療者)、フォローアップ・ミーティングを開きます。冒頭、看護師がそれまでの「患者カルテ」を参加者に配布し朗読します。それをスタートにして「開かれた対話集会」が始まります。すべての参加者は対等に扱われ、水平な治療空間が創られていきます。患者は、「患者カルテ」が看護師との共同コミュニケとして発信され、自分がその対話空間の主人公であり、参加者間で交わされる自分についての言及を第三者的に聞き及ぶに至って、自らへの新たな知見を手にしやすくなります。その朗読はまた、看護師との連帯と協力関係を参加者に示す「祝祭的」な意味をも持ち合わせます。「他者の苦しみへの責任」を看護師が負うことで、それが患者にとっての足場となり、回復に向け大きく前進します。
「患者カルテ」は、ナラティヴ、コラボレイティヴ、オープンダイアローグを活用した日本発の家族療法です。当日詳細をお話しますが、事前情報をという方は、下の文献が全文読めます。よかったら参考になさってください。当日みなさんの質問に出会えることをたいへん楽しみにしています。
The patient-authored medical record: A narrative path to a new tool in
psychiatric nursing.
DOI: 10.1016/j.apnu.2022.03.009
Patient-authored medical record II: A not-knowing approach to psychiatric
nursing.
DOI: 10.1016/j.apnu.2024.06.012
大会企画講演3
9月5日(金)15:30~17:30
家族療法における基礎としての複数面接
講師:吉川悟(龍谷大学心理学部)
司会:大平厚(カウンセリングルームIRIS)
家族療法の発展経緯、特に1960年代を概観すれば、個人面接と複数面接の決定的な差異が、家族療法に対する「新たな心理療法・精神療法としての期待」が向けられていた根拠である。この決定的な差異となる視点の違いは、様々な個人の精神内界に対する「個人心理学に基づく理論」と、複数の人間の相互作用における「コミュニケーションのあり方」であった。
この差異は、家族療法の認識論がシステム論から社会構成主義に変化しても、実践に反映できるのかが重要である。今後の家族療法の展開に意味がある議論の入り口と位置づけ、家族療法の基礎としての複数面接について再考することとする。
大会企画講演4
9月5日(金) 13:30~15:00
家族療法から学んだこと:家族システム理論、一般システム理論、DBT, トラウマインフォームドアプローチ、サンクチュアリモデルなどにおけるシステムの広がりと深まり
講師:遊佐安一郎(長谷川メンタルヘルス研究所)
コメンテーター/リフレクター
梁田秀麿先生(東北福祉大せんだんホスピタル)
福井里江先生(東京学芸大学)
田中究先生(関内カウンセリングオフィス)
数多く一見混沌としているようにも見える心理的支援の分野を整理してみると、次のような分類の仕方も可能ではないだろうか?
- フロイト、ロジャースやベックなどの個人アプローチ、
- システミックアプローチ、ナラティブアプローチなどの家族アプローチ、
- 弁証法的行動療法、トラウマインフォームドケア(アプローチ)やソマティックアプローチなどの生物―(心理)―社会アプローチ、
- そしてトラウマインフォームドアプローチやサンクチュアリモデルのなどの組織システムなどのレベルでの支援アプローチ
私は自分を振り返ってみると、臨床の世界に入って、苦悩を経験している人(自分を含め)の理解と苦悩の緩和の工夫に興味を持って行動してきたと要約することもできるような気がしている。当初は目の前の個人に焦点を当てておりC, Rogers(Person-Centered Approach)やG. Kelly(Personal Construct Theory)などの影響を大いに受けてきた。1970年代後半から始めた精神病院の急性期病棟での仕事で、患者さんたちから直接、そして主に間接的にその家族との関係の重要性を教えてもらってきたころから家族療法に興味を持って学んできた。その時に大きな影響を受けたのが家族システム理論である。特にL L. BertalanffiやJ. Van Gigchなどの一般システム理論(Geeral Systems Theory)での対象の広がりと、J. Millerの一般生物システム理論(General Living Systems Theory)の影響は時間とともにじわじわと私に刺激を与えてくれたような気がする。
約50年にわたるこのような当事者、その家族、仕事仲間などとの関係から学んできた自分のプロセスを振り返って、フィードバックをもらえれば、私にとってさらなる刺激になることを期待して。