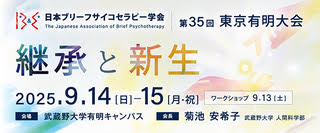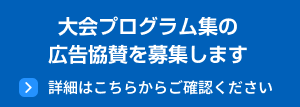9月16日(金)16:30~18:30
大宮大会では、これから家族療法を学ぶ人や初学者向けに、家族療法のポイントや、家族支援における重要なテーマを扱ったミニワークショップを企画しました。大会会期内の1企画として設置され、いずれも2時間で、ワークショップの体裁ですが、大会の参加申込をしていれば無料でご参加いただけます。興味のある方は、ぜひ当日会場へお越しください。
9月6日(土)10:10~12:10
1.複数面接の基本~関係をみる、関係と関わる~
大平厚(カウンセリングルームIRIS)
家族療法に興味や関心を持ち臨床実践に取り入れるための試行錯誤をし始めると、システムや関係性、相互作用などの見慣れない視点を学ぶだけでなく、“複数面接”という見慣れない面接形態での実践を考える必要が生じます。この複数面接という面接形態は、多くの情報と可能性を実践者に与えてくれるものではありますが、個人面接とは異なる前提やポイントを持つため、「個人面接の視点のみではその個性を活かすことが難しい」と感じたり、「実践そのものをイメージしにくい」と思われるかもしれません。
本WSでは、“複数面接による実践のための「目(視点)」と「意識」と「振る舞い」”に焦点をあて、その基礎的な内容をお話しします。また、実際の振る舞いや留意点などに関する擬似的な体験を通し、「関係」そのものにコミットする複数面接の初歩に触れる機会になればと考えています。
9月6日(土)13:30~15:30
2.必要性から考える「ジョイニング」入門
田中智之(神戸医療未来大学)
ジョイニング(Joining)は、ミニューチン(Minuchin,S.)が提唱した、構造的家族療法における家族との関係構築のための重要な方法論です。日本では構造派に限らず、さまざまな家族療法のオリエンテーションにおいて、実践すべき基本的手続きとして広く認識されています。
しばしばジョイニングは、アコモデーション、トラッキング、マイムという3つの具体的方法として紹介され、これらの方法を通じてクライエントや家族のルール、役割などにセラピストが合わせ仲間入りするというのが一般的な理解だと思います。
初学者の方にとって、これら具体的な説明によりどのような手続きかを理解しやすい一方で、ジョイニングをトレーニングしたり実践したりする際に、家族療法の実践全体にどのように結びつくのか実感しづらいことがあるかもしれません。「ジョイニングが上手くできているかいまいち手応えがない」「合わせてみたけど何に繋がるのかよく分からない」といった状態になることも少なくないのではないでしょうか。
このミニワークショップでは、「なぜ家族療法にとってジョイニングが必要なのか」という必要性の視点から、あらためてジョイニングの手続きについて考えたいと思います。単なる関係構築の手段にとどまらず、相互作用を仮説化するための手段としてジョイニングを学んでいただける機会となることを目指したいと思います。
9月5日(金) 13:00~15:00
3.ジェノグラム入門:その情報の豊かさに触れてみましょう
藪垣将(藪垣心理療法研究室)
ジェノグラム(Genograms)は、定められた表記法に従って、少なくとも三世代にわたる家族メンバーや家族の関係性についての情報を記録・図示するものです。といっても、ジェノグラムは単に家族関係や基本的な属性などの情報を図示するものではありません。それらの情報に加えて、世代を超えて繰り返されるパターン、生物学上の系譜を超えた世代間相互作用を取り扱います。
ジェノグラムを作成するのに必要となる基本的な情報は、主にアセスメントの初期の段階で収集されます。一方で、ジェノグラムは介入のための有用なツールとしても用いることが出来ます。
本ワークショップは、基本的なジェノグラムを描けるようになること、そしてジェノグラムをある程度読み解けるようになることを到達目標と致します。
ジェノグラムを臨床に活かせるようになるためには、ジェノグラムをたくさん作成し、検討し、その扱いや解釈に習熟する必要があります。本ワークショップは、その最初の足掛かりとなることを目指します。
さらに、臨床上のさまざまな工夫や、専門家教育の一環としてのジェノグラム・インタビューなど、臨床場面以外での運用方法についてもご紹介します。
9月5日(金)15:30~17:30
4.思春期・青年期家族へのアタッチメント理論に基づく支援
稲垣綾子(日本女子大学)
Bowlbyが提唱した危機時に発動する対人的な行動システムであるアタッチメントは、生物が備えている基本的なニーズで、私たちが生き延びていくのに不可欠なものです。アタッチメントニーズの受け手である大人は子どものSOSに出会うと、ケアしようという気持ちや衝動を高め、養育システムを発動させます。アタッチメント関係は、一方がどうニーズを伝え、もう一方がそれにどう応答するかという経験のくりかえしによって形作られます。これは成人同士の関係でも基本的に変わりません。
しかし、思春期・青年期から成人期にわたってニーズの表現は複雑化します。ニーズが伝わらなかったり、それを受け止めにくかったり、その内容が誤解されたままだったりすると関係の悪循環が生じます。
また、アタッチメントには個人差があり、心の危機時に出会うことの多い臨床では、家族メンバーそれぞれのアタッチメントシステムで何が起き、悪循環のパターンが引き起こされるのかを理解することで、その手当を考える文脈を家族に提供する道が拓かれます。
Bowlby 自身も臨床において、現実の家族との関わりを重視し家族合同面接を取り入れました。家族療法が大事にしてきたシステム論、構造論、多世代論とも相性のよいアタッチメントの視点を、近年の潮流であるアタッチメントベースドプログラムの紹介も含めて共有したいと思います。
9月6日(土)15:45~17:15
5.ヤングケアラーへの支援を考えるー精神疾患のある親と暮らす子どもを中心にして
長沼葉月(東京都立大学人文社会学部)
2024年の子ども・若者育成支援推進法の改正により、ヤングケアラーは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義され、制度的支援の対象として位置づけられるようになりました。
しかしヤングケアラーという総称は、支援者から状態像を把握するのに便利であったとしても、当事者である子ども・若者からは葛藤を引き起こす言葉ともなっています。本ワークショップにおいては、私の主たる研究テーマである「精神疾患のある親と暮らす子ども」を中心にその生活体験についてまずご紹介します。
「日常生活上の世話を過度に行う」という表現だけでは把握しづらい暮らしの困難の諸相をお伝えすることで、「家事負担の量、時間」を代行することで減らす、という発想とは異なる視座で支援の在り方を考えていただきたいと思います。
利用可能な福祉サービスや制度についても開発してきたツールを用いながら紹介します。最後に、参加者同士で「あたかも事例検討会」を行ってみましょう。
支援者の視座が広がることで、関わりの手立てや方策が増える経験につながることを願っています。