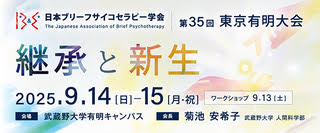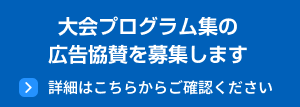9月7日(日)10:00~16:00
- ワークショップは参加手続きの完了(参加費の支払いを含む)による先着順となります。定員に達した場合のみ、第2希望、第3希望のワークショップになることもございます。ご承知おきください(基本として第1希望になります)。
- 参加申込フォームにて、第1希望、第2希望、第3希望のワークショップの番号(1~7)を入力してください。
- ワークショップの決定・確認のためのメールを、大会前に大宮大会のアドレスomiya2025@jaft.orgから連絡させていただきます。メールが届くように、メールフォルダの設定をご準備ください。
1.子ども・若者に身近な依存症と、その家族へのアプローチ 薬物依存症のACE当事者の立場から
風間暁(特定非営利活動法人ASK)
ネット・ゲーム、市販薬など、今もっとも大人たちが「わからない」嗜癖対象に、子ども・若者はのめり込んでいる。そんな子ども・若者の依存症支援に際し、「子ども・若者本人」と、「親を中心とした周辺の大人たち」へのアプローチを学ぶ、専門職・支援者対象のワークショップ。
講師のACE(Adverse Childhood Experiences:子ども期の逆境体験)〜物質使用障害の体験談をもとに、人を信用できなくなった仕組みを解説。それから、現在の子どもたちを取り巻く世界の実際を共有しつつ、子どもの権利に根差した関わりや、具体的に効果のある声かけの方法、目線の合わせ方などを、子どもたちと直接関わり続けている講師とのロールプレイなどを通じて学んでいく。
このワークショップを通じて、子どもたち自身の権利を無視した大人の独善的な支援をなくし、子どもにとって意義深く、尊重される実感が得られるような支援が増える社会を目指す。
2.質的研究入門―理論的背景とデータ分析の基礎
能智正博 (東京大学大学院教育学研究科)
質的研究はここ30年ほどの間に心理学、教育学、看護学など人間・社会科学の諸分野で急速に広がってきた、質的データを扱う研究法の総称である。家族療法の実践者・研究者の間でも関心をもつ方々が増えており、学会での発表や学会誌への投稿も増加している一方で、研究方法の妥当性や内容などに懸念がある発表や論文原稿も散見されるとも聞く。現在では質的研究法の教科書は非常に多く出版されているが、大学等の研究法の授業等でトレーニングを受けてそのスキルを身につける機会をもてた人はまだ少ないかもしれない。本ワークショップでは、質的研究に関心をもちつつまだ研究実践にまで踏み切れない人や、自力で質的研究を行ったもののまだしっくり来ていない人に向けて、質的研究の入門的な講義とワークを提供する。具体的には、まず質的研究を行う上での土台となる認識論など哲学的な背景を簡単にお話ししたあと、サンプルデータを用いながらそのテクストを丁寧に読み、グラウンデッドセオリーなどで用いられるコード化・カテゴリー化のワークを行う。具体的なデータを扱うことにより、よりいっそう実感を伴う形で質的な分析の過程を体験してもらえればと思う。また、時間が許せば、近年アメリカ心理学会が発表した質的研究論文の執筆基準(質‐JARS)の内容にもふれたい。
3.RC:認証と可能性の探究から実践を振り返るナラティヴ・スーパービジョン
国重浩一(ナラティヴ実践協働研究センター)
RC(リフレクシヴ・コンバセーション)は、ナラティヴ・セラピーの哲学や姿勢を基盤とし、リフレクティングの構造を用いた、グループ・スーパービジョンの一種です。ここでは、事例(話題)を提供する人の取り組みを認証し、今後の関わりの可能性を探究しながら、実践を振り返る協働的な会話の場となります。
事例検討のように参加者が自分自身の興味のために、クライアントや事例(話題)提供者を分析したりするのではなく、参加者は、クライアントや事例(話題)提供者を中心に置き、そのために考え、発言していきます。
RCは、「教える」「指導する」のような多くの人にとってなじみのあるような方法ではなく、認証と可能性の生成を基盤とする場において、人は活力をもらい、その上で、これからの取り組みのヒントをもらいながら、成長できるのだという、新しい学びを提案するものです。
このワークショップにおいて、RCの考え方、構造(プロセス)を説明し、デモンストレーション、ワークをしていきたいと考えています。
4.家族療法入門 ~実践を始める上で大事なこと~ 【定員50名】
村上雅彦(広島ファミリールーム)、岩田尚大(広島大学病院)
家族療法は関係性の視点・文脈から問題や出来事を理解しようとする支援者の姿勢が求められます。しかし、実践をしようとした途端に、支援者は目の前の家族と展開している支援の状況をどのように理解したらいいのかと、難しく感じてしまうことが少なくありません。
このワークショップは家族療法を学んだことがない方(初学者と自覚する方)、日々奮闘している現場に部分的にでも取り入れたいと考えている方、そして書籍などを通して家族療法に触れ始めたけれどこれからどのように学んでいけばいいのか困っている方を対象とします。そして、参加者が相互にディスカッションしながら、家族療法の実践を始める上で必要な事柄を体験的に学んでいきます。プログラムとして、前半部分は【理屈編】です。家族療法の全体的な輪郭や流れなどをおさえながら、目の前の家族との状況に関する理解の仕方を学んでいきます。後半部分は【体験編】です。模擬事例などを用いて家族療法を実践する上で必要な支援者の目を養うことや家族への関わり方を体験してみることにも取り組む予定です。
家族療法の基本を対面で学べる機会はそう多くはありません。是非、ご参加をご検討ください。お待ちしております。なお、このワークショップは前回大会(金沢大会)のワークショップ(家族療法入門)と類似の内容となります。
5.ロールプレイングによる家族・夫婦同席面接の演習 【会員限定:定員25名】
中村伸一(中村心理療法研究室)
北島歩美(日本女子大学カウンセリングセンター)
岩井昌也(錦糸町クボタクリニック)
宮崎愛(富士カウンセリングオフイス)
なかなか具体的な面接法の指導を得る機会が少ない会員のためのWSです。負担の少ないロールプレイをおこないながら、来談者たちとどのようにコミュニケートするかということを具体的に学ぶことができます。いわゆるジョイニング、多方面への肩入れ、関係性へのパラフレージングとその「関係性へのジョイニング」が基礎的な技法となりますが、円環的な仮説、構造的な仮説を構築し、いくつかの期待されるべき変化の方向性を考えてみましょう。そこではポジティブなリフレイミングや行動処方などがありますが、チューターと話し合いながらそれらにも挑戦することができるでしょう。また家族や夫婦役割をしてみることで来談者の立場に立ってみるという経験も大変に貴重なものとなるでしょう。時間はたっぷりに見えますが、あっという間に時間がたつのが今までの参加者の感想です。楽しく実践してみることのできるWSです。奮ってご参加ください。
6.トラウマインフォームドな家族支援に向けて【定員25名】
遊佐安一郎(長谷川メンタルヘルス研究所)
西田泰子(常葉大学短期大学部)
中垣真通(子供の虹情報研修センター)
唐津尚子(北浜心理臨床オフィス)
去年は児童虐待の家族支援の工夫としてトラウマの視点を組み込むことをテーマにワークショップを行いました。最近のトラウマに関する理解の進歩により、虐待に限らず様々な形のトラウマが個人にそして家族に影響をあたえる可能性が考えられます。トラウマの影響が顕著な問題の一つである感情調節困難に関しても家族関係の様な身近な人間関係はその癒しのためにも、逆に増悪の悪循環の関係としても相互影響は大きく、家族支援はそこでも重要な役割を持つと考えられます。
トラウマインフォームドな家族支援の在り方について興味を持っている参加者と理解と支援の工夫の仕方について情報を共有し、実践にどのように組み込むことが出来るかについてともに学ぶ時間を持ちたいと思っています。
7.家族・関係者からの支援を主眼とした発達障がいの当事者への支援―システムズアプローチの視点からの対応―
吉川悟(龍谷大学心理学部)、志田望(龍谷大学心理学部)
「発達障がい」だけではないが、障がいに対する社会的な支援の広がりと、多様性に対する理解の促進が推奨されるようになった。しかし、今もって発達障がいへの支援の基本が「当事者への支援」に重きが置かれ、日常的に当事者を支援しよう、関与しようと考えている家族や関係者がどのように関わることが有効なのかについての指針が、圧倒的に欠落しているように考える。
本ワークでは、基本的な「発達障がい」当事者への対応の是非論とは異なり、家族や関係者に対する積極的な関与を促進することを前提としたい。そのためには、①当事者の現状や今後に関しての期待、要請、希望など、どのような要望があるのかと、②家族や関係者が当事者に対して持っている要望、という異なる2つのそれぞれのニーズを明確にすることを前提として、そこで ③今後の希望を紡ぐためのコンセンサスの構築のための複数面接のあり方を示すこと、その演習を行いたい。
可能であれば、複数面接の研修受講や実践的経験などがあることが望ましいが、参加者からの希望があれば、上記の①②を明確にするための要点についてもふれる予定である。